卒業論文の中でも特に多くの人がつまずく「考察」のパート。「何を書けばいいのか分からない」「結論とどう繋げればいいの?」「読み手を納得させる表現って難しい」…そんな悩みはありませんか?
実は、近年のAIツールを使えば、こうした悩みはかなり軽減できます。AIは単なる文章生成だけでなく、構成づくりや論理的な展開、表現の見直しまでカバーしてくれる心強いパートナーです。
当サイト(AI文章研究所)では、卒論の考察が書けないというお悩みを解消する方法を掲載しています。ChatGPT以外でも主要なAI(Google Geminiなど)であれば同じことが可能です。
卒論の考察がスムーズに書けるAI活用法
結論から言えば、「考察パートでAIを活用する」最大のメリットは、“論理の組み立て”と“客観的な視点”をサポートしてくれる点です。
構成案の提案、先行研究との比較、文章表現の改善など、AIができることは多岐にわたります。
その結果、「何を書けばいいかわからない」という状態から、「自分の研究の意味や意義をしっかり表現できる」状態へと導いてくれるのです。
考察パートでAIを活用する3つのステップ
- 考察の構成をAIに相談する
- 先行研究との比較をAIで補助
- 表現力を高めるAIの文章チェック
考察の構成をAIに相談する
まず手を付けるべきは「構成」です。
AIに「考察の流れを提案して」と聞くだけで、適切な構成案が返ってきます。たとえば以下のようなアウトラインです:
- 研究結果の要点
- 先行研究との比較
- 予想と異なる点
- 結果の社会的・学術的意義
- 今後の課題
こうした形で、AIに頼れば構成段階で迷う時間を短縮できます。詳しい構成テンプレートは「ChatGPTで卒業論文を書く完全ガイドとテンプレート」でも紹介しています。
先行研究との比較をAIで補助
考察では、あなたの研究が既存の研究とどう違い、何を新しく示しているかを述べる必要があります。
ここでAIに「〇〇に関する先行研究の要点を要約して」と依頼すれば、文献のポイントをすばやく抽出できます。
その情報をもとに、自分の研究の意義や位置づけを明確にしましょう。先行研究の例文を参考にしたい方は「卒論の実践例文テンプレート14選」もご覧ください。
表現力を高めるAIの文章チェック
ある程度文章を書いたら、AIに「この文章を推敲して」と頼むと、より論理的で読みやすい文に修正してくれます。
特に考察では論理の飛躍があると評価が下がりがちなので、客観的な視点での校正は非常に有効です。
「語尾の被り」「抽象語の多用」なども、AIは即座に指摘してくれます。
卒論考察でよくある質問(Q&A)
Q1: AIに考察を書かせるのはズルでは?
A: AIは“補助ツール”です。構成や表現のヒントをもらうのはOKですが、内容の判断や最終的な表現は自分で行いましょう。参考資料のように活用すれば問題ありません。
Q2: ChatGPT以外でも使える?
A: はい。Google Gemini、Claude、Notion AIなど、同様の機能を持ったAIツールも使えます。どのツールでも、基本的な使い方と効果は共通しています。
Q3: 具体的な例文がほしいです。
A: 「卒論の実践例文テンプレート14選」にて、実際の例文を公開していますのでぜひ参考にしてください。
まとめ:AIで“考察が苦手”を乗り越えよう
考察は、卒業論文の中でも特に「何を書けばいいのか分からない」と悩みやすいパートです。
しかしAIツールを活用すれば、構成の組み立て、先行研究の整理、文章のブラッシュアップまで幅広くサポートを受けられます。
この記事で紹介したステップやツールを活用しながら、自分の言葉でしっかりと意味ある「考察」を書き上げましょう。
構成から執筆まで一貫して活用できるテンプレートは「ChatGPTで卒業論文を書く完全ガイドとテンプレート」でも紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。

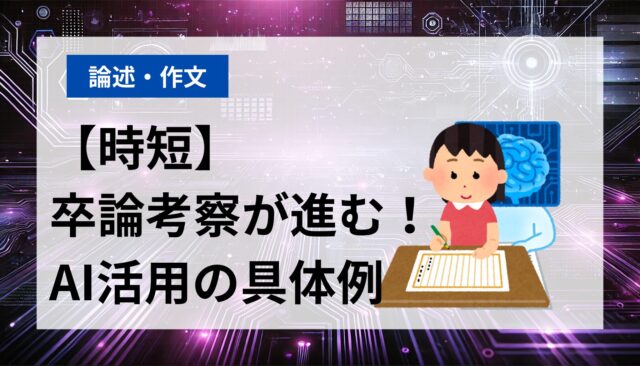
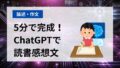
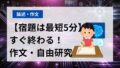
コメント